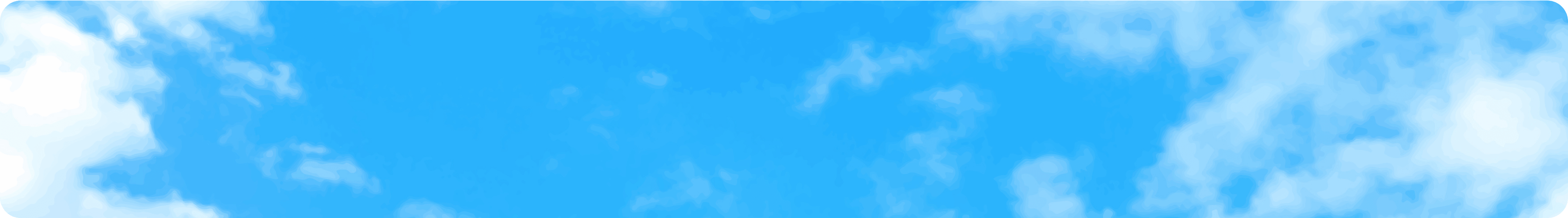コーラ10000えん
年長B組に自動販売機が登場しました。
ジュースづくりから発展した遊びのようです。
商品名や値段がしっかり書かれているのは、このクラスが夏前から取り組んでいたお祭り遊びで培ってきた学びの一つ。
経験したことを駆使して遊びを広げていくことはとても豊かな学びです。
(コーラ10000えんは高いですね笑)
そんな自販機の前に立って、あれこれ話している子どもたち。
遊びを通じて意見を出し合うことも、これまた豊かな学びです。
さらに、定規を持ち出して長さを測り出す子も。
何の長さを測っているのかは不明ですが、この姿も重要。
国が定める「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の中の一つに、
「数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚」というものがあります。
解説書においては
「5歳児の後半になると,それまでの体験を基に,自分たちの遊びや生活の中で必要感をもって,多い少ないを比べるために物を数えたり,長さや広さなどの量を比べたり,様々な形を組み合わせて遊んだりすることなどを通して,数量や図形への興味や関心を深め,感覚が磨かれていく」(幼稚園教育要領解説、P.63、太字筆者)
とあります。
さらに、
「その際,一人一人の発達の実情などに即して,関心がもてるように丁寧に援助するとともに,幼児期には,数量や文字などについて,単に正確な知識を獲得することを目的にするのではないことに十分留意する必要がある」(同、P.64、太字筆者)
ともあります。いわゆる文字や数字のお勉強をさせることが目的ではないのですね。
そして、
「こうした幼児期の数量や図形,標識や文字などへの関心や感覚は,小学校の学習に関心をもって取り組み,実感を伴った理解につながるとともに,学んだことを日常生活の中で活用する態度にもなるものである。」(同、P.64、太字筆者)
と締めくくられています。
遊びのなかで、自然に文字や数に触れることで子どもたちに「実感を伴った理解」や「学んだことを日常生活の中で活用する態度」が育まれ、それが小学校以降の学習を支える根っこになるということです。
すみません、つい長くなりました(悪い癖です)。
この時期に、豊かな環境を通して、いろんな経験をすることがとても大切で、
その経験を保障することが私たち保育者の役割なのだと思います。